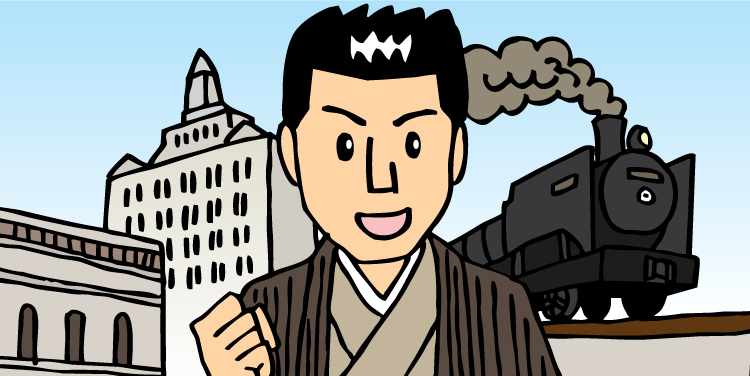
第5回銀行に就職
走り使い、つらい毎日
二年後に上京し本店勤務
「共栄貯蓄銀行で事務見習いを募集している」ということを耳にしたのは、野菜の呼び売りにうんざりしているときだった。野菜売りも実際にやってみると、「だいこーん、にんじーん」という呼び声ひとつさえ、容易に口から出るものではなかった。お前なら採用されるかもしれないよ、と母にも励まされて応募してみると、幸いに試験にはすぐ通った。月給三円五十銭の事務見習い、私は十六歳になっていた。
それから二年後、本店勤務となって上京するまでの間、私はこの事務見習い、といっても給仕のような仕事に日を送ったのだが、その間に痛切に感じたことは、やはり勉強をしなければ一人前の世渡りはできないということであった。最初は全く給仕扱いだった。
「おい、おれの泥ぐつをあらっておいてくれ」「自転車がよごれているからそうじしろ」「タバコをちょっと頼む」といったぐあいでとても事務を覚えるどころではなかった。支店次長の尾上という男などは、好きな芸者へのラブレターまで届けさせたりした。私がしぶしぶ置き屋へ持っていって女に渡すと、半玉みたいな妓(こ)が「はいおだちん」といって、五銭か十銭を握らせた。私はその金をいきなり地上にたたきつけた。自転車や泥ぐつ程度ならまだしも、芸者にラブレターを届ける役など、私にはがまんがならなかったのだ。
それでも、しばらく勤めているうちにソロバンや伝票書きを少しずつ覚えるようになった。そして月給も五円になった。そのころから私は、自分の知識の不足を痛感しはじめたのである。少しむずかしい単語が出てくるともうわからない。上の人に聞くと、そんなことは自分で勉強しろ、といわれるだけだ。横で聞いている話も、ほとんどわからない。いつまでこんなことをしていてもしょうがない、と気づくと、私は猛烈に向学心が燃えてくるのを自覚した。
勉強しなくてはだめだ、どうせ苦労するのなら、東京へ行けばなんとかなるかもしれぬ、夜学でもなんでもよい、勉強しなければと思うと、私はその気持ちをそのまま父に打ち明けた。父はむろん私の考えを認めた。とにかく勤める身なのだから支店長さんに相談してみろといわれて、おそるおそる支店長にうかがいをたててみると、意外な道が開けてきた。本店の星野という常務が、ときどき支店にも見回りにきていたが、「あの男ならかねて見込みがあると思っていたから、本店によこしてみてもよい」と返事をしてくれたのである。
全く天にものぼるような気持ちだった。本店は東京の鎌倉河岸にあった。私はまもなく書記補という資格をもらい、上京して本店勤務をするようになったのである。大正七年のことで、初任給は四十二円五十銭だったと思う。寸暇を惜しんでも勉強したいという私の意欲に同情してくれたのか、ありがたいことに銀行に現金を持ってゆく仕事を与えられた。人力車に乗ってゆけるので、車の中でも本が読めるし、銀行で待っている時間も利用できた。
私は勉強の場をいろいろ調べて、中央大学の専門部(夜間)を受験しようと考え、まず基礎を固め夢中で勉強した。上京して、職にも恵まれ、自分で本気でやろうという気になっていたから、真剣でもあり、楽しかった。神田の小川町、麹町の富士見町、本郷と、私は安下宿をわたり歩いて、勤めながら学校に通う生活を続けたが、銀行勤めだから服装などは月賦でもある程度きちんとしていなければならぬし、学資も出してゆく、私の月給ではどうにも足りない。東京の生活もひと口にいえば貧乏暮らしの極であった。
(日本経済新聞:昭和37年2月25日掲載)※原文そのまま
